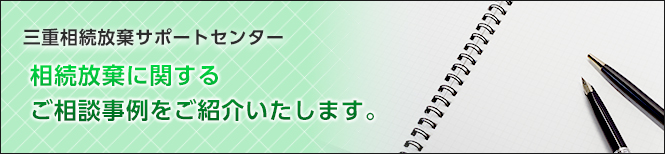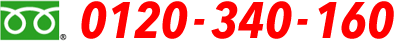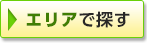2020年12月09日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄をする際、他の相続人に連絡をとる必要はありますか?(四日市)
四日市在住の母が一カ月前に亡くなりました。父は既に他界しているので、相続人は姉と私だけです。現在は相続手続きを進めている段階です。生前母の所有していた財産と負債の整理を行っているのですが、母は四日市に一軒家といくつかの不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、借金も抱えていたようで負債もありました。姉と私は現在疎遠状態で相続手続きも私のみが行っている状態です。連絡を取りたいのですが、なかなか取れず手続きが進みません。さらに姉は四日市からも離れて暮らしております。これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄をする際も他の相続人と連絡をとる必要はあるのでしょうか。一人で相続放棄することは出来ないのでしょうか。是非教えて頂けたらと思います。(四日市)
A:一人でも相続放棄をすることは可能です。
結論から申し上げますと、一人でも相続放棄することは可能です。相続放棄は一人ひとりの相続人が個人で行うものです。よって、相続放棄の手続きをする際、他の相続人と協力して行う必要はありません。ご相談者様はお姉様と疎遠状態であるようですが、疎遠状態の方がいる場合は後々トラブルにならないようご自身から相続放棄をされる旨の連絡だけはしておいた方が良いでしょう。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。ご相談者様の場合は四日市を管轄する家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりませんので、期日が経過する前に手続きを行いましょう。なお、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多かったということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということができませんので、相続放棄をする場合には慎重に手続きを行う必要があります。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明がおありの方や被相続人が住んでいた場所から離れた場所にお住まいでなかなか相続手続きを進められないという方は専門家に依頼することをおすすめします。相続手続きについてお困りでしたら専門家に依頼して解決するという手段もありますので、ぜひご検討いただければと思います。
四日市にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は、三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。三重相続サポートセンターは相続手続きにおける専門家が集まっております。相続放棄に関する手続きも丁寧にご対応させていただきます。
四日市の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年11月26日
Q:亡くなった父の遺産を相続しました。その後借金があることが判明したのですが、遺産相続後でも相続放棄は可能でしょうか。司法書士の先生にご教示頂きたいです。(鈴鹿)
2ヶ月前に父が病気で亡くなりました。父は母と鈴鹿市の自宅で暮らしておりましたが、母も5年前に亡くなっています。私は兄と姉の3人兄妹で、現在、私は鈴鹿のマンションで暮らしており、兄は京都、妹は東京で暮らしています。兄妹で話し合った結果、父が所有していた鈴鹿の自宅は、今後空き家となってしまうので売り払うことにし、売却金を受け取りました。
しかしその後、私の知らないところで父に多くの借金があることが判明し、返済するよう言われてしまいました。ですが、借金が多く、私がすぐに返済できる額ではなかったので、相続を放棄したいと考えています。遺産を相続してしまった後でも相続放棄することは可能でしょうか?(鈴鹿)
A: 相続放棄ができる期間は原則3か月以内と規定されていますが、既に遺産を相続してしまっている場合は放棄することが出来ません。
この場合、ご相談者様は、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を相続する「単純承認」という相続をしたとみなされます。たとえ相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、既に相続財産の全部、または一部を処分してしまっている場合は、単純承認をしたことになってしまいます。また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続の放棄」をしなかった場合も、単純承認が成立してしまいます。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになります。
そのため、相続人の方は相続開始から3ヶ月以内に何らかの行動を起こす必要があります。また、今回のケースのように遺産相続後にマイナスの財産があったことが判明する場合もあります。そのため、ご自身が相続人となった際には、専門家に相談するのが良いでしょう。すべての遺産をきちんと確認した後に、相続放棄をするか否かを決めるほうが安心して、相続を進めることができます。
三重 相続放棄サポートセンターでは、主に相続放棄を専門に取り扱っております。相続放棄のことならどんなことでもご相談ください。分かりやすく、丁寧にお答えいたします。専門家が無料で相談を承っておりますので、鈴鹿周辺にお住いの皆様、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
2020年10月26日
Q:相続放棄の期限について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)
四日市在住の60代女性です。5カ月前、同じく四日市市内に住んでいた兄が亡くなりました。兄は結婚しており、妻と息子が2人います。兄の結婚式以来、私と兄の家族は疎遠になっており、お葬式には参加したものの、特にそのあと連絡を取ることもなく過ごしてきました。ところが先週になって、債権者を名乗る人から兄の借金返済を要求する通知が私宛に届いたのです。突然のことで大変驚き、どうして私が返済しなければならないのか、疑問に思って債権者に問い合わせてみたところ、兄嫁とその息子たちはすでに相続放棄していたことを知りました。私と兄の両親も、祖父母も亡くなっているため、自動的に私が相続人となり、借金返済を求める通知を送ったということだったのです。私も素人なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だということがわかりました。しかし、兄が亡くなってからそろそろ半年になります。長年、親交もなかった兄の借金を返済しなければならないことに、どうしても納得がいきません。私が兄嫁の相続放棄を知ったのは先週のことですが、私は相続放棄できないまま、兄の借金を返済することになるのでしょうか。(四日市)
A:最近、相続放棄されたことを知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の相続放棄のお悩みは三重 相続放棄サポートセンターにおまかせください。
相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。ご不安に思われていたように、被相続人が亡くなられた日から数えるわけではありませんのでご安心ください。ご相談者様はお兄様の死亡日から5カ月後にはじめて自分が相続したことをお知りになりまりました。ですので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。債権者から請求書が届いたのも最近のようですから、すぐに家庭裁判所へいき相続放棄の手続きをしましょう。稀に、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいい、と解釈してしまうこともあるのですが、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は「法律を知らなかった」という理由は認められませんので注意をしてください。
三重 相続放棄サポートセンターでは、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。はじめてのご相談は無料ですので、相続に関する疑問やトラブルはぜひ三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。四日市のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年09月07日
Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続放棄の期限内に手続きが終わるか分からないのですが、どうすればよいですか。(鈴鹿)
先月、鈴鹿で一人暮らしをしていた母が他界しました。父は数年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人になります。母が負債を抱えていたのですが、鈴鹿の実家や預貯金などの相続財産の調査をしきれておらず、相続するか相続放棄をするか迷っています。財産調査に思っていたよりも時間がかかっていまして、相続放棄の期限までに間に合わないかもしれないと焦っております。しかし、財産調査を終えてから考えたいと思っていますので、どのようにすればいいか悩んでおります。何かよい方法があれば教えていただきたいです。
A:期限内に終わらない場合、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」という制度を活用しましょう。
相続放棄をする際は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、相続があることを知った日から3ヶ月以内に申述をしなくてはなりません。もしも期限内に申述をしなかった場合、プラスの財産も負債もすべて相続すると承認されてしまいます。しかしながら、ご相談者様のように故人の相続財産を把握しきれていない状態で期限が到来してしまうケースもあります。そうした場合は、家庭裁判所へ相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。家庭裁判所の判断により、相続放棄の期限延長が認められると1~3ヶ月程度の期間、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
ご相談者様のように相続か相続放棄か判断がつかなかったり、両親が離婚をしていたりして、財産調査に時間がかかり相続手続きが思うように進まない方もいらっしゃいます。分からない部分があるのにもかかわらず、焦って相続手続きを進めてしまうとトラブルに発展してしまうこともありますので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄が可能な期間は、相続があることを知った日から3ヶ月以内と短く、延長期間があったとしても、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要となり、時間がかかります。期限内に相続放棄の手続きを終えられるかご不安な場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿を中心に相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿近隣にお住まいの皆様からのご来所を心よりお待ちしております。
2020年08月08日
Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄をしたいのですが可能ですか?(四日市)
四日市の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人である母と、兄と私で相続手続きを進めております。父は四日市にいくつか不動産を所有しているのもあり、プラスの財産もありますが、負債もあるようです。兄は四日市の実家の近くに住んでおりますが、私は四日市から離れて住んでおり、実家のことは兄の方がよくわかっています。今後の相続手続きの事を考えると色々手続きも大変そうなので、私は相続放棄をしようかと考えています。私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。(四日市)
A:ご相談者様だけで相続放棄はできます。
相続放棄は、相続人各々が1人で行うことができます。
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。したがって、ご相談者様の場合、四日市市を管轄する家庭裁判所へ申述をすることとなります。
尚、相続放棄には自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。
一度相続放棄の手続きをすると、被相続人に負債があるので相続放棄をしたが、後々財産を確認したら負債よりプラスの財産の方が上回り、最終的にプラスの財産が手元に残るという事が分かった場合でも、「やはり相続します」ということはできません。相続放棄は受理されると撤回することはできませんので、ご検討されている場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご自身で行う場合でも慎重に手続きをしましょう。
相続放棄や財産の調査は知識がないと、ご自身で手続をするのは難しい点もあるかとおもいます。手続きの方法や手順について不明点がある方や、ご自身で行うのが不安な方は相続の専門家にご相談ください。また、被相続人と離れた場所にお住まいの相続人の方は、相続手続きに負担を感じる方も少なくありません。そのような場合にも専門家に手続きを依頼することが可能です。ご自身での手続きに不安があり、ご負担に感じられる場合には専門家に依頼するという方法も解決策の一つです。
被相続人が四日市にお住まいだった相続人の方や四日市にお住まいの相続人の方で、相続放棄についてご検討されている方は三重 相続放棄サポートセンターまでご相談ください。三重 相続放棄サポートセンターは相続放棄の専門家として、三重の皆様の手続きをサポートいたします。
四日市エリアで相続放棄に関するご相談なら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。
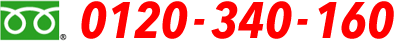
- 電話受付時間:平日9時~17時